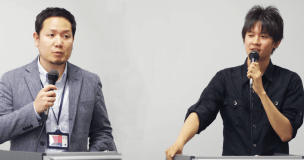
※本記事は株式会社Ptmind提供によるスポンサード・コンテンツです。
【第1部】API連携で無限に広がるスパイラル(R)を使ったマーケティングオートメーション(株式会社パイプドビッツ 河田大介さん)
 河田大介さん(株式会社パイプドビッツ コミュニケーション戦略プランニング部 部長)
河田大介さん(株式会社パイプドビッツ コミュニケーション戦略プランニング部 部長)
2020年、日本のMAツールの市場規模は200億円を超える見込み
現在、アメリカでは70%の企業がMAツールを活用しており、市場規模も2400億円に達しているそうです。 日本でここ数年、大きな成長が続いており、前年比150%で成長。2020年にはその規模は200億円を超えるとも言われています。 参考:Marketing Automation insider:ITR Market View:マーケティング管理市場2017結局、使いこなせない!費用対効果が合わない!は、MAツールでよくある大きな課題
しかしさまざまなことができる分、機能の数が非常に多いMAツール。いくら高価なツールを導入しても、高機能過ぎるツールは使う側もスキルが必要になり、結局使いこなせない、ということも起こっているそうです。 大切なのは、たくさんの機能があることではなく、経営課題を解決できること。MAツールの費用対効果は、担当者がツールを使いこなせること、自社の課題を解決するということまで含めて考える必要があります。 そのために「まず、自分たちがどういう課題があるかを明確にアウトプットすること。課題が明確でないと課題を解決する手段に過ぎないMAは活用できません。」と、河田さんは話します。戦略・シナリオを考えて、どういう課題を解決するのか?を明確にする重要性
それでは具体的にどういうことをしていけばいいのでしょうか?MAツールを導入する時、よくあるのは下記のようなプロセスです。 ① 戦略設計 ② シナリオ設計(ペルソナ、カスタマージャー二―) ③ 実装 ④ 運用 この中でも特に自社に合ったMAツールの選択に重要な、戦略設計についてもう少し掘り下げていきます。戦略設計の2つのコツ
1.課題の認識 まず、自社の課題を洗い出し、MA導入によって成し遂げたいゴール・目的を設定します。例えば、MAツールの目的を「見込客の管理/育成を目的としたマーケティング業務の効率化や効果の向上」とすることもできます。 2.購買プロセスの可視化 課題が分かったら、ユーザーの購買行動を可視化し、仮説を構築していきます。そのためにはペルソナを作成しターゲットを明確にすることが重要です。そのペルソナを含めてカスタマージャーニーの作成をすることで、見込み客の購買プロセスをより良く理解することできます。カスタマージャーニーマップは、その後のMAでリードナーチャリングのプロセス設計を行う際にも有効なツールです。 またMAツールの導入目的によっては、ステップメール、ポップアップ、クーポン、サイト行動分析、細かなスコアリング…などさまざまな機能が必要です。ただし、自分たちに必要な機能や、自分たちのこれまでのITシステムの状態にあった課題解決は1つのMAツールだけで実現できるとは限りません。 そこで重要なのが、API連携。つまり他のツールと組み合わせてツールを使うこと、だと河田さんは話します。株式会社パイプドビッツが提供するスパイラル(R)もMAツールと連携ができるそうです。詳しい活用事例は後半でご紹介します。【第2部】オートメーションとデータが導く顧客体験と企業アクションの最適化(株式会社Ptmind 安藤高志さん)
 安藤高志さん(株式会社Ptmind Co-Founder)
20世紀、馬車から自動車に景色が変わるのにかかったのにかかったのはたった13年でした。ところがマーケティングの世界の変化はもっと速く、たった1年でも景色が変わってしまうそうです。実際にMAツールにもそういった波が来ている、と安藤さんは話します。
安藤高志さん(株式会社Ptmind Co-Founder)
20世紀、馬車から自動車に景色が変わるのにかかったのにかかったのはたった13年でした。ところがマーケティングの世界の変化はもっと速く、たった1年でも景色が変わってしまうそうです。実際にMAツールにもそういった波が来ている、と安藤さんは話します。
この3年でMAツールは「ユーザー体験を向上させるため」のツールに
マーケティングに関するテクノロジーをまとめたカオスマップ2014年、2015年には、「バックボーンプラットフォーム」と呼ばれ、インフラに近い技術だったMAツールは、2016年から「コンテンツ&エクスペリエンス」というカテゴリに、位置づけが変更になりました。 これが意味するのは、「MAツールの目的は、ユーザーの体験を上げるものである」と再定義されたということ。ユーザー体験を最適化するために、マーケターがするべきなのはデータを統合的に見て、アクションを最適化することだそう。 参考:Marketing Technology Landscape Supergraphic (2017): Martech 5000 - Chief Marketing Technologist顧客体験とアクションを最適化するために押さえておきたい3つの事実
それでは、もう少し細かく、押さえておきたい3つのテクノロジートレンドをご紹介します。①オープンAPIの数が、急速に増えている。
オープンAPIの数は急激に伸びていて、2005年には186だったものが、2016年には15,799にもなっているそうです。 オープンAPIによって各社がサービスを他社製品と連携できるようにしていることで、あらゆるサービスが自社や他社ツール・データと連携がしあえる環境が整いつつあります。②アメリカでは、高機能な1ツールを入れるよりも、それぞれの会社に合ったツールを入れるほうが効果的という結果が出た
アメリカのWalkersands communication が、2017年に335社のマーケティング責任者にした調査では、「1つのツールだけを使っている企業よりも、複数のツールをうまく組み合わせて使っている企業の方がマーケティングの成果を高い」と感じていることが分かりました。 このことからも、高性能なツールな1つのツールの活用だけではなく、会社の各所に最適化されたツールを連携させるという考え方の重要性が増しています。③分業主義+AIが今後のカギに
各所に最適化されたツールの情報は、どんどん蓄積されていきます。その情報がAIによって、パフォーマンスが最適になるように自動化されていくのではないか、と安藤さんは話します。ツールを選ぶ前に、連携ができるかどうかの確認を
上記の理由から、これからツールを選ぶときは「他のツールやデータと連携ができるのか?」も確認するべき、と安藤さんは話します。 それでは、実際に連携とはどういうことができるのでしょうか?実際に“組み合わせる”ってどういうこと?MAツールとの連携事例
河田さん、安藤さんのお話から、複数のツールを組み合わせて使う重要性は分かったものの、実際にはどうやって連携をしていくのでしょうか?セミナーの中でご紹介されていた、スパイラル(R)と、DataDeckとMAツールの連携事例をご紹介します。MAツール×スパイラル(R)で、安全性の高いデータの活用が可能に
 株式会社パイプドビッツが提供するスパイラル(R)は、様々なシステムやアプリケーションと連携ができるマルチデータ活用アプリ作成プラットフォームです。「情報資産の銀行」というコンセプトの通り、100社以上の金融機関に採用されるほど高いセキュリティが特長です。
参考 :スパイラル(R)特長:https://www.pi-pe.co.jp/spiral-series/spiral-suite/feature/
スパイラル(R)はMAツールなどと容易に連携できます。またメール配信の機能は、最高配信時速140万件を誇る高速配信エンジンを用意。そのため、Web上の行動情報の取得、スコアリングをMAツールで行い、その情報をスパイラル(R)のデータベースに保管し、セグメントを切ったメール配信やステップメールの配信なども可能です。
例えば、無料で使えるオープンソースのMAツールMauticとスパイラル(R)を組み合わせることで、その基幹になるセキュリティレベルが高いデータベースとして活用されているそう。
その事例としてセミナーの中で紹介されていたのは、不動産の会社です。例えば、最初にサイトに登録した時には吉祥寺に興味を持っていたユーザーが、しばらく経ってから下北沢の情報を調べ始め、月に何回も訪問をするようになったとします。そういう行動が分かれば、下北沢に関する情報を、メールやLINEなどで積極的にユーザーに配信できる、という仕組みです。
株式会社パイプドビッツが提供するスパイラル(R)は、様々なシステムやアプリケーションと連携ができるマルチデータ活用アプリ作成プラットフォームです。「情報資産の銀行」というコンセプトの通り、100社以上の金融機関に採用されるほど高いセキュリティが特長です。
参考 :スパイラル(R)特長:https://www.pi-pe.co.jp/spiral-series/spiral-suite/feature/
スパイラル(R)はMAツールなどと容易に連携できます。またメール配信の機能は、最高配信時速140万件を誇る高速配信エンジンを用意。そのため、Web上の行動情報の取得、スコアリングをMAツールで行い、その情報をスパイラル(R)のデータベースに保管し、セグメントを切ったメール配信やステップメールの配信なども可能です。
例えば、無料で使えるオープンソースのMAツールMauticとスパイラル(R)を組み合わせることで、その基幹になるセキュリティレベルが高いデータベースとして活用されているそう。
その事例としてセミナーの中で紹介されていたのは、不動産の会社です。例えば、最初にサイトに登録した時には吉祥寺に興味を持っていたユーザーが、しばらく経ってから下北沢の情報を調べ始め、月に何回も訪問をするようになったとします。そういう行動が分かれば、下北沢に関する情報を、メールやLINEなどで積極的にユーザーに配信できる、という仕組みです。
 他にも、
・レコメンド情報の活用
・コンテンツマーケティング×Web接客ツール×スパイラル(R)
・プライベートDMP×スパイラル(R)
などの活用方法が紹介されていました。
参考:スパイラル(R)シリーズ : https://www.pi-pe.co.jp/spiral-series/
参考:お客様事例 : https://www.pi-pe.co.jp/showing/
他にも、
・レコメンド情報の活用
・コンテンツマーケティング×Web接客ツール×スパイラル(R)
・プライベートDMP×スパイラル(R)
などの活用方法が紹介されていました。
参考:スパイラル(R)シリーズ : https://www.pi-pe.co.jp/spiral-series/
参考:お客様事例 : https://www.pi-pe.co.jp/showing/
ツールで集めたデータをDatadeckでまとめ、分析・改善へ
 また組み合わせによって利用するツールが増えると、必然的に確認するべきデータも増え、煩雑になりがち。よりデータを効果的に使うには、それらの情報の一元管理が必要です。DataDeckは、Google アナリティクスやAdWordsをはじめ、さまざまなデータをまとめて見られるツールです。特にWebの専門家ではなくても簡単に使えるように作られています。
例)DataDeckで作ったLISKULのダッシュボード
DataDeckを使えば、データの統合、ビジュアライゼーション(データの可視化)、統合したデータのURLでの簡単なシェアが可能です。事例としてご紹介されていたスポーツサービス会社さまでは、URLで情報を普段はこういったITデータを専門で使わない部署にも打ち合わせなどで瞬時に共有し、改善のスピードを早めているとのこと。
このように、データを見やすく共有しやすい状態にしておくことで、複数の関係者・関係部署との連携を円滑にしています。
参考:経営層と現場のデータ活用のギャップを埋める!「DataDeck」の魅力とは?
また組み合わせによって利用するツールが増えると、必然的に確認するべきデータも増え、煩雑になりがち。よりデータを効果的に使うには、それらの情報の一元管理が必要です。DataDeckは、Google アナリティクスやAdWordsをはじめ、さまざまなデータをまとめて見られるツールです。特にWebの専門家ではなくても簡単に使えるように作られています。
例)DataDeckで作ったLISKULのダッシュボード
DataDeckを使えば、データの統合、ビジュアライゼーション(データの可視化)、統合したデータのURLでの簡単なシェアが可能です。事例としてご紹介されていたスポーツサービス会社さまでは、URLで情報を普段はこういったITデータを専門で使わない部署にも打ち合わせなどで瞬時に共有し、改善のスピードを早めているとのこと。
このように、データを見やすく共有しやすい状態にしておくことで、複数の関係者・関係部署との連携を円滑にしています。
参考:経営層と現場のデータ活用のギャップを埋める!「DataDeck」の魅力とは?
まとめ
さまざまなテクノロジー、ツールが登場する現在。1つのサービスだけに頼るのではなく、さまざまなツールの組み合わせで、自社にあった状況を作りやすい環境は整ってきています。 ぜひ自社の状況を見直し、適切なツールの連携について考えてみてはいかがでしょうか?「DataDeck」のご案内
DataDeckはデータを統合し、事業データの集約/管理/分析を統合するサービスです。 事業パフォーマンスのあらゆるデータをビジネスマンが簡単にセルフサービスで接続をしてチームやステークホルダーに共有できます。データはすべて自動更新され、常に最新の事業情報を一人一人が確認できます。使いやすさと要件に合わせたカスタマイズの自由度が最大の特徴です。 DataDeckのサービスはこちらから https://www.datadeck.jp※本記事は株式会社Ptmind提供によるスポンサード・コンテンツです。